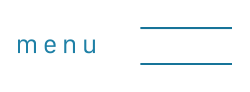ある日書棚を眺めていると、岩波文庫が数冊埋もれており、こんなの読んでたかなと取り出してみるとその中にJ.S.ミルの『功利主義』がありました。薄い書籍なので読んでみようと思ったのかも知れません。内容は覚えていませんでした。何の勢いか、読んでみようと思い立ち。
功利主義が、その言葉のイメージと異なることを主張していることぐらいは理解しているつもりでしたが、改めて気付かされることもありました。
書籍の内容そのものは、いわゆる「最大多数の最大幸福」の追求について、質的な視点も加えるべきだとの主張が主だったものです。あとは外的な動機づけや内的な動機づけ、正義についてなど。
さて、読了後、今の仕事と何か関連するのか?といったことを考えてみました。
現在耳にする人事テーマではやはり若い世代を中心とした給与水準の向上でしょうか。各社競って初任給を上げたりしており、私のクライアントでもその対応に苦慮されています。給与水準が向上しているにも関わらず、離職の流れが止まらないというのも併せて伺います。もちろんより高い給与を求めて転職する人もいますが、それだけではないようです。
ミルの師であるベンサムが功利主義を唱えた際、最大多数の最大幸福を量でとらえていました。この観点で人事施策を考えると、高い給与水準、各種手当、福利厚生、都心にある快適なオフィスビル。このあたりを中心に考えていくのが量を最大化するアプローチでしょうか。
これを質も含めた形で最大化せよというのがミルの言っていることだとすると、どのようなことが考えられるのか?それが内的動機づけ(制裁)などとの関連でいくと、エンゲージメントなり、well-beingなり、心理的安全性なりといったワードが出てくるということなのでしょうか。
以下、ミルの功利主義に対応して最大多数の最大幸福を質的側面から追求するための内容を検討してみました。
1)組織の個人のむすびつけ
会社の事業、ビジネスが成長し、拡大することが最も重要ではあることは前提として。
会社の存在意義、MVVなどと個人の仕事や価値観をつなぐこと。自らの仕事に目的を見出すこと。
2)キャリアの個別最適化
画一的なキャリア観やモデルではなく、個別に質の高い幸福を追求できるようにすること。
今はリスキリングや兼業などの手法ぐらいしか思い浮かびませんが、より多様な世界と交わる機会をつくること。
3)管理職の役割変化
コーチングや1on1の考え方などが浸透してきていますが、上記1)2)を進めるにあたって管理職に期待するところはやはり大きいかと。
管理職が個人の幸福について、質的な側面を見出すこと。
また、人事施策としては、評価制度において、量的で短期的な業績数値だけではなく、未来に向けた挑戦や取り組みといった質的な側面をしっかりと評価していくことが重要となるのでしょう。
100年以上前の古典ではありましたが、少し上記について思いを巡らせることができました。薄めの書籍なのでおすすめです。