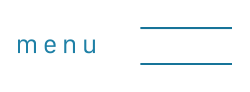私も60をとうに過ぎ、老人の道を順調に歩んでいます。このような老人にもお仕事いただけてとてもありがたく思っていますが、果たして自分は使い物になっているのだろうか、老害ではないのだろうかと、不安になることがあります。
老害とは一般的に年配者が職場の中で周囲の人の足を引っ張るような言動をする人を言い、例としては、次のようなものがあります。
・周囲の意見には耳をかさず、自分の意見を押し通す
・部下や後輩の提案を否定する
・昔はよかった、昔の社員の方ががんばっていたと過去を美化して説教する
・聞いていない、間違いを認めない、すぐに感情的になる 等々。
老害と言われる人とそうでない人は何が違うのだろうか?
現在の研究成果を基に考えてみたいと思います。
知能には流動性知能と結晶性知能という2つの知性があると言われています。
流動性知能とは、新しい環境に適応したり、新しい問題にぶつかったりした時に発揮される力で、新しい情報を獲得し、処理・操作する知能です。18歳~25歳頃をピークに徐々に低下していきます。
一方、結晶性知能とは、経験や学習などから獲得する知識や知恵、判断力、応用力などの能力です。言語力に強く依存し、洞察力や理解力、批判や創造の能力などが該当します。
結晶性知能は、成人期を通じて増え続け、60代くらいで頂点を迎え徐々に低下すると言われていますが個人差が大きいことや加齢の影響を受けにくく高齢になっても比較的維持できる知能と言われています。

(出所:https://courses.lumenlearning.com/suny-lifespandevelopment/chapter/crystalized-versus-fluid-intelligence/ から引用)
「老害」と言われる人は、流動性知能の衰えを認識せず、自分の過去の成功体験や方法論に固執する傾向があるのではなか。それに対して「老害」と言われない人は、結晶性知能を活かしつつ、流動性知能の衰えを補うために学び続け、新しい知識やスキルを柔軟に取り入れるのではないかと思うのです。
パーソル総合研究所によると、シニアが転職市場で活躍できる条件には、「変化適応力」(トランジション・レディネス)が重要な要素であるとしています。変化適応力とは、「会社・ビジネス・環境に変化が生じてもうまく対応できる」という自己効力感のことで、仕事でパフォーマンスを発揮するだけでなく、積極的に自己研鑽を続け、必要があれば、新たなスキル・知識が必要な職域に転向する積極性のことです。
つまり、流動性知能を補う意識を持っている人がシニアになっても活躍が期待できるという示唆を与えてくれています。
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/202108160001.html
と考えると、経験学習サイクルがとても大切な意味を持っているのではないでしょうか。
年齢を重ねても時代に合わせて変化を受け入れる柔軟性を持ち、「経験→振り返り→理論化(学び)→実践」のプロセスを繰り返し、自らの知識やスキルを進化させ続ける意欲。また、他者と協力するコミュニケーション能力と自分よりも若年層の方からも学ぶ力、こういった要件を満たす人材は、単なる経験の多さではなく、現代の課題に対して新しい視点や価値を提供できる「変化の担い手」として評価されるのではないかと思います。
「老害」と言われないようにするには?と問いを立ててきましたが、「老害」とか、年齢がどうのこうのではなく、学びと成長に対する姿勢によるところが大きいと思いました。企業組織が求めるのは年齢を問わず、自己成長と柔軟性を備えた人材で、上記のような姿勢を持ち、つねに自己成長を続けることができる人材と思います。そんな人材がどんな年齢であっても活躍の場を広げることができる、そう思いました。