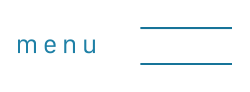正直に言えば、こうした「衰え」について自ら語ることには、少なからず躊躇があります。人前で話す職業柄、弱さや変化を公にすることが、これまで築いてきた信頼やプロとしての評価に影響するのではないか、そんな不安もあります。一方私は人事の領域で活動する者として企業が抱える「シニア人材の活躍」には強く関心を持っています。シニアが自らの変化をどう受け止め、どう次の価値に変えていくのか――その問いに自ら向き合い、率直に語ることこそが、同世代やこれからシニア期を迎える方々へのエールになると信じ、今の心境を書くことにします。
今年、私は還暦を迎えました。最近ふと気づくと、人前で話している最中に言葉が出てこないことがあります。かつてなら瞬時に言葉が浮かび、場の空気に合わせて自在に話せていたのに・・・。場に起きていることへの反応スピードも、わずかに鈍くなっていることを自覚しています。
脳科学的には、これはごく自然な現象のようです。前頭前野の機能が加齢によりゆるやかに低下し、「ワーキングメモリ(作業記憶)」の容量が減っていく。ワーキングメモリとは、一時的に情報を保持しながら同時に処理する能力。例えば、会話をしながら次の発言を考える、複数の情報を瞬時に整理する、そうした力が少しずつ弱まっていくのです。
しかし一方で、若い頃にはなかった手応えもあります。経営者や管理職の方々から、「理屈だけじゃなく、実感として伝わってくる」「なぜか自然と話せてしまいます」「話していると、自分の強みや価値に気づくことができます」のような言葉をいただきます。これは心理学で言うところの「結晶性知能」の高まりかもしれません。年齢を重ねる中で培ってきた経験知、洞察力、状況を俯瞰する視点、そして人の心情に寄り添う力。それらが、自分の中で深まっているのかもしれません。
また細かな説明は省きますが、高齢期になると「社会情動的選択性理論」の影響で、人生の有限性を意識し、「今、ここで大切な人との関係性」や「意味ある体験」を重視するようになると言われています。私自身、仕事においても「この人に何を残せるか」「この時間にどんな価値を生み出せるか」といった視点が、以前よりも明確になってきています。
「できなくなること」を嘆くのではなく、「できることの質を高める」――これが今、私が最も意識していることです。若い頃は体力にものを言わせた仕事、瞬発力や情報処理能力で勝負もしていましたが、少し時間的な余裕を持ちつつ、じっくりと大切に思える人のために、できる限りの価値を提供できるように努力したいと考えています。
還暦を越えてからの人生は、「衰え」を受け入れながらも「深まり」を武器に、もう一段自分を進化させるステージ。人生後半戦は、これまでとは違う尺度で、自分らしい貢献の形を模索していく。私もそんな生き方をこれから目指していこうと思う今日この頃です。